| こだま通信 Vol.48 2005年3月号 2P(障子は世界に誇るインテリア) |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
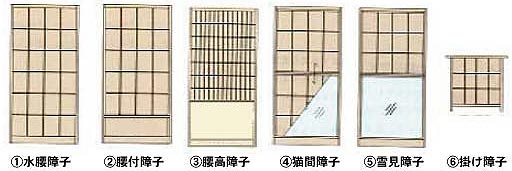 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
障子 |
|
|
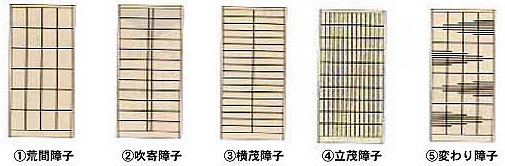 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
ものを写真化したものです。→ |
 |

