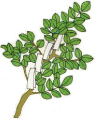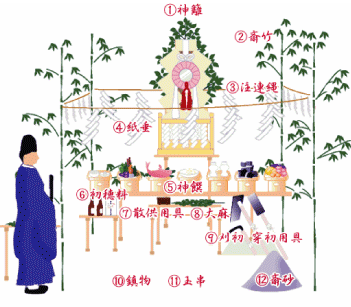| こだま通信 Vol.51 2005年6月号 2P(日本古来の伝統〜地鎮祭の儀〜) |
日本では、古くから家を建てるとき、祭り事が必ず行われてきました。地鎮祭は、一般に「ぢちんさい」や「ぢまつり」と言っていますが、正しくは「とこしずめのまつり」と読みます。
地鎮祭は、私達の人生にも誕生以来いろいろな区切りがあり、その時々にまつりを行い無事繁栄を祈ることと同じく、建築を行う場合も着工にあたり、その土地の守護神に無事完成を祈願する大切な祭りです。
最近は土地の浄化ばかり注目されますが、本来の意味は違います。
日本には八百八の神様が居られ、土地を所有されています。その神様の所有されている土地に、勝手に家を建てて神様のお怒りに触れないように、土地を借りるための『土地借用の儀式』これが地鎮祭なのです。家が完成した時には、地鎮祭で借用の契約をした神様を祀るために神棚を設け神札(おふだ)をおまつりすることも大切です。 |
|
地鎮祭の順序と作法 |
(1)修祓(しゅばつ)の儀
参列者の心身を祓い清めて、神に近づく行事
(2)降神(こうしん)の儀
払い清めた祭場に神をお迎えする行事
(3)献饌(けんさん)の儀
神様のお食事となる神饌を供える行事
(4)祝詞(のりと)奏上
これから土地をお借りして家を建てることを神様に報告し、工事の安全を祈願する行事
(5)切麻散米(きりぬさんまい)の儀
祭壇に供えられた神酒、米、塩、切木綿を中央・四隅にまいてお祓いする行事
(6)鍬入(くわいれ)の儀
苅入(かりそめ→鎌入れ)および穿初(うがちぞめ→鍬入れと鋤入れ)の行事
鎌入れ…設計者 鍬入れ…施主 鋤入れ…建設業者
(7)玉串奉奠(たまぐしほうてん)の儀
玉串を捧げ、神への崇敬の心を表す行事
(8)撤饌(てっせん)の儀
神官が神前に進み、神饌を上げる行事
(9)昇神(しょうしん)の儀
降神の儀でお迎えした守護神を元の御座にお返しする行事
(10)直会(なおらい)の儀
関係者が、神饌の神酒のおさがりを頂戴して、関係者の和楽を尊ぶ行事 |
|
|
玉串(たまぐし)ってなに? |
| 玉串とは、“たましいのくし”という意味です。つまり、人間の魂と神様の魂を一つに結ぶ串なのです。真心を込めてお祈りをした後、その願いを確実にするために人間の心が神様の御心と一つに結ばれることが大切です。玉串奉奠とは、目に見えない心と心の結びつきを、あたかも目に見える行為を通すことによってパフォーマンスをしているのです。しかし、これはあくまでも一つの説です。他にも、「玉」は美しいもの、素晴らしいもの(例えば上玉(女性の例)、玉虫(美しい色)、玉の輿(きれいな乗り物)、玉砂利(丸くてきれいな石)など)を指し、「串」は髪にさすくし、人間の頭(頂点)に付けると美しくなる、エネルギーを持つ、という意味が込められているという説もあるようです。 |
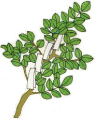 |
|
|
祭典用具 |
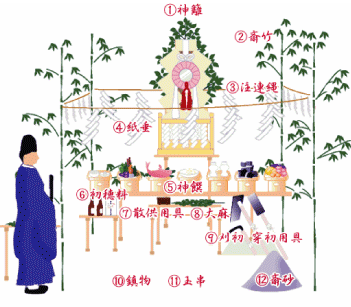 |
なぜ竹が必要なの?
竹は最も成長の早い植物で、古代の人々はその成長にエネルギーを感じ、そこには神が宿り悪魔を退治してくれると考えられていたようです。祭場では竹を4本立てて、その間にわら縄を張ります。縄は結界(特別なエネルギーの場所)の境界と生成を表現しています。縄張りをすることで境界を表現しているのです。竹があって始めて縄が張れるわけで、竹無しでは結界は張れません。結界を張らずに地鎮祭を行っても、その場所の鎮魂だけでなので、厄介なものも入って来てしまいます。
|
|
(1)神籬(ひもろぎ)…榊に紙垂(しで)や鏡、麻をつけたもので、お祭りにあたりお降り願う神霊の依代(よりしろ)として設ける。
(2)斎竹(いみだけ)…神様を迎える清浄な場所の表示として、青竹を祭場の四隅に立てる。(1辺約2メートル四方)
(3)注連縄(しめなわ)…竹の上部約2メートルの高さで右奥(艮(うしとら)の方=東北)の隅より時計回りに張りめぐらす。
(4)紙垂(しで)………斎竹・注連縄と同じく清浄な所としての表示
(5)神饌(しんせん)…神饌は神様に捧げるお供え物です。四季おりおりの新鮮な物を選ぶことが大切です。塩・水・果物・野菜・海草・魚・米・酒など
(6)初穂料(はつほりょう)…祭典の奉仕にあたり、神社への謝礼をのし袋に入れて奉納する
(7)散供用具(さんくようぐ)…四方四隅を祓い清め供物をして地霊を鎮めるためのもので、紙と麻を切ったもの(切麻(きりぬさ))と、米、酒、塩など
(8)大麻(おおぬさ)…神様をお迎えするにあたり、祭場、神饌(しんせん)、参列者等を祓い清めるための祓具(はらえのぐ)で、榊や白木に紙垂や麻を付したもの。
(9)刈初・穿初用具(かりぞめ・うがちぞめようぐ)…施主及施工者が初めてその土地に手をつけることを神前に奉告する儀式。
(10)鎮物(しずめもの)…地霊を、和(なご)鎮める為に捧げる物で、人像(ひとがた)・刀・矛・盾・鏡等を辛櫃(からひつ)に納めて埋納する。
(11)玉串(たまぐし)…榊の小枝に紙垂(しで)をつけたもの。
(12)斎砂(いみすな)…盛砂ともいい、鍬入れの儀に用いるため、祭場の近くに円錐形に砂を盛る。 |
|
|
※地鎮祭は、各地方や建造物により多少内容が異なるようです。 |
|